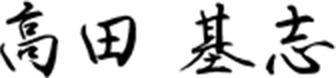院長挨拶

日頃より格別のご支援を賜り、心より御礼申し上げます。新たな年度を迎えるにあたり、総合大雄会病院院長として改めてご挨拶申し上げます。
おかげさまで、私ども社会医療法人大雄会は昨年、創立100周年を迎えることができました。地域の皆さまに支えられ、100年の永きにわたり医療・介護を通じて社会に貢献できましたことを喜ばしく思うのと同時に、大変誇らしく感じております。
さて、私も院長となり丸3年が経過しました。これまで、コロナの話ばかりでしたので、今年こそは違う話題にしようと意気込んでいたのですが、今度はインフルエンザです。コロナほど騒がれることはありませんでしたが、2024年から2025年にかけての年末年始は、インフルエンザ患者さんの急増により、当院でも押し寄せる多くの救急患者さんを断らざるを得ない状況に陥りました。同じような事態は日本全国でみられ、図らずも急性期医療の脆弱性を露呈することとなりました。本来であれば、いつ如何なる時も救急患者さんを受け入れられる体制を整えておくことが急性期病院の使命なのですが、それが叶わないのが日本の医療の現実です。
独立行政法人福祉医療機構のデータによれば、急性期一般入院料1を算定する病院(いわゆる急性期病院)の56.7%が赤字経営に陥っていることが明らかになりました。しかも、これは2023年度のデータです。昨年、実施された診療報酬改定では、医療費削減が叫ばれる中、プラス改定ではあったものの、その改定幅はわずか0.88%にとどまり、インフレによる材料費の高騰には遠く及びません。2024年度の急性期病院を取り巻く環境がさらに悪化していることは火を見るより明らかです。世間では5%を超える賃上げが浸透してきていると景気のいい話が聞こえてきますが、医療業界ではその原資すらままならないのが現状です。このままでは、医療や介護の業界からより魅力的な業界に人材が流出し、回復不可能な人手不足に陥るのではないかと大変危惧しております。
「2025年問題」という言葉を耳にしたことがある方も多いでしょう。これは、団塊の世代が全員後期高齢者になることで生じる諸問題を指しますが、その本質は高齢者の急増から現役世代の急減へと社会の局面が変わることにあります。現役世代、すなわち生産年齢人口が減り続ける中、この先誰が高齢者を支えるのか? 団塊の世代は団塊ジュニアが支えることができます。しかし、その団塊ジュニアが高齢者となったとき、いったい誰が支えるのでしょう? 私が危惧している医療・介護人材の流出が現実のものとなったとき、私たちは今よりさらに厳しい状況を目の当たりにすることになります。そんな誰も望まない未来にならないよう、私たちは今から声を上げ、行動しなければならないのです。
未来を変えるカギは「協業」にあります。今ある医療資源を有効かつ効率的に活用するには、多くの医療機関が協力して、地域の医療を「面」で支えることが重要です。そのためにはお互いの情報や設備、人材までも共有する仕組みが必要なのです。一朝一夕でできることではありませんが、立ち止まっている暇はありません。どんなに困難であろうと、最初の一歩を踏み出さなければならないのです。
ならば、その役割を私たちが果たしましょう。大雄会のモットーは「進取の精神」です。常にファーストペンギンであり続けることに誇りを持っております。未来を変えるための一歩を誰よりも先んじて踏み出しましょう。次の100年に向けての歩みが、みなさんの望む未来につながるよう精進を続けてまいります。これからも、引き続きご期待賜りますようお願い申し上げます。
総合大雄会病院院長